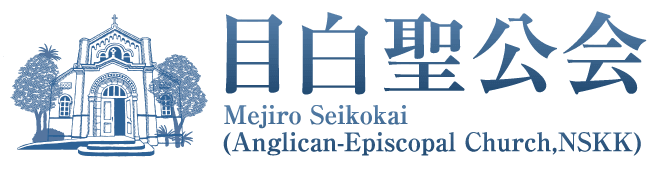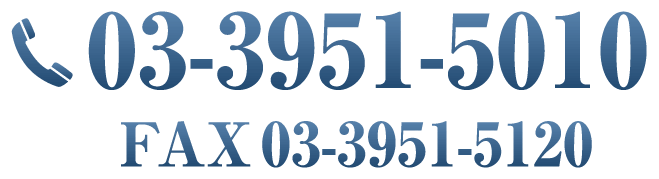「主の名によって来られる方に、祝福があるように」
(ルカによる福音書13:31-35)
イエスがエルサレムへ入るとき弟子の群れから「主の名によって来られる王に祝福が
あるように。・・・」(「・・・主の名によって来られる方に祝福があるように」マタイ・マルコ・ヨハネでは群衆)と大きな声(神への賛美を込めて)で迎えられました。これは、ファリサイ派、律法学者、祭司長のようなエルサレム神殿の近くでユダヤ教の宗教的指導を担っていた人々にとってある意味、脅威となりました。そのことを示唆する場面としてイエスがエルサレムの神殿で繰り広げられたであろう彼らとの激しい問答にあります。
なぜ、激しい問答となったのか?それにはある理由があります。イエスの語った神の国(神の支配)とは、ユダヤ教が生み出した聖別思想(聖なる者と汚れた者)を超越する思想ゆえに彼らにとっては受け入れがたいことでした。それと同時に汚れた者とされた者たちがイエスによって癒されて共感する声が大きくなること(静かにさせられた人たちが立ち上がる)はユダヤ教の宗教的指導者たちにとっては自分たちの立ち位置を揺るがしかねない恐れでもありました。
エルサレムでイエスが歩む十字架の道は人々からの排斥の極みであり、エルサレムで迎えられたときの様子とは異なります。この排斥の心は宗教的指導者だけではなく、イエスと共感していた人たちの心にも伝染(イエスへの共感の先にイエスが宗教的指導者を一掃してくれると思いこんだある意味、個々の欲望の裏返しとして)しました。また、イエスの生きた当時の政治的指導者であるガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスとユダヤの総督ピラトにおいても人間の罪性が滲み出てしまいます。
ヘロデ・アンティパスと敵対関係にあったユダヤの総督ピラトがイエスをエルサレムに来ていた自分のところによこしたことにより(イエスがガリラヤの人であったので)、ピラトがヘロデ・アンティパスの地位(ガリラヤの領主としての)を認めたということ、そして、イエスを死に追いやることへの責任回避(ピラト自身もユダヤ人群衆にイエスの十字架刑の責任を負わせた)という点で利害関係が一致したという点です。
すべての人の罪を引き受けようとするイエスは自分が十字架の上で死ぬことで、自分を十字架につけたユダヤ人たちもまた、一緒に死ぬことを35節で示唆します(見よ、お前たちの家は見捨てられる)。そして、イエスが復活してすべての人(ユダヤ人に限らず)が赦されて救われと後(イエスが復活して昇天した後)、主の来臨の予言として『主の名によって来られる方に、祝福があるように』というみ言葉をわたしたちに語りかけてくださっています。主に感謝です。
(司祭ウイリアムズ藤田 誠)
ホーム >
「主の名によって来られる方に、祝福があるように」
2025年3月15日
礼拝案内 Service
日曜日(第一日曜日を除く)
Sunday(except for first Sunday)
7:30 聖餐式 (Holy Communion)
9:30 日曜学校 (Sunday School)
10:30 聖餐式 (Holy Communion)
17:00 夕の礼拝 (Evening Service)
第一日曜日 first Sunday
9:30 日曜学校 (Sunday School)
10:30 朝の礼拝 (Morning Service)
17:00 夕の礼拝 (Evening Service)
■10:30からの礼拝には手話通訳があります。
聖日 Holy Day
7:30 聖餐式 (Holy Communion)
アクセス・地図 Access/Map
目白聖公会
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-19-4
3-19-4, Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-0033, Japan
TEL:03-3951-5010
FAX:03-3951-5120